
私は、4年ほど前にウスカワマイマイの赤ちゃんを飼育したことがきっかけで、カタツムリについていろいろ調べるようになりました。今回は、前回に引き続き、海外のカタツムリの生物学者の活躍を解説します。
なぜ、日本のカタツムリの学名は外国人が学術記載が多いのか

私は、野外でカタツムリを観察しながら、名前などを調べています。詳しく学名を調べると、外国人の(Pfeiffer)という名前を目にすることが多くなり、「なぜ、日本のカタツムリなのに、外国人の学者が記載しているのか、それにAcusta sieboldtianaってシーボルトのことなのか🤔」と不思議に思ったことがあります。そこで今回は、この疑問を解く鍵となる、ドイツの生物学者シーボルトとファイファー(Pfeiffer)、キュースター(Küster)、マルテンス(Martens)の業績を紹介しながら、日本の陸貝分類学の黎明期の一端をご紹介します。
鎖国の壁と「未知の日本」の衝撃

私たちが今、身近なカタツムリの学名を調べられるのは、19世紀のヨーロッパの博物学者のお陰です。なぜなら、19世紀の当時のヨーロッパの学者にとって、鎖国下の日本は「学術的な空白地帯」だったからです。そして、シーボルトの功績によって、日本文化や自然が世界に紹介されました。ただし、シーボルトが海外に持ち出した日本の生物の標本は必ずしも、万全の状態では無かったようです。
この状況を、後に日本の貝類研究を深化させたドイツの学者、エドゥアルト・フォン・マルテンス(E. von Martens)は、1865年の論文冒頭で以下のように記しています。
「日本の陸貝や淡水貝については、プロイセンの遠征隊が出発する前はほとんど知られていなかった。(中略)シーボルトが1823年から1830年にかけて日本で集めた、決して少なくない陸貝と淡水貝の標本は、ライデン(オランダ)の王立博物館で(未分類のまま)手つかずの状態で置かれていた。」
論文:「東アジアへのプロイセン遠征:公的資料による」より引用(上記は原文の翻訳)
※参考資料 Die Prussian Expedition nach Ost-Asien, Zoology(アーカイブ)

マルテンスの言葉が示すように、シーボルトが持ち帰った日本の標本は、残念ながら、すぐに調査されず、未分類のまま放置されていました。中には採集地が分からなくなり、「モルッカ諸島」のものと誤認されるなど、情報が錯綜していました。
この歴史的な混乱を収拾し、日本の生物相を世界に紹介し始めたのが、ドイツの二人の学者、キュースターとファイファーでした。
1847年:日本の貝類分類学の黎明期
私は今回、日本の陸貝に与えられた国際的な学名の最古の記録をたどることで、この黎明期の様子を考察しました。
萌芽期(1844年)
キュースターは1844年に、後年に日本のキセルガイとして記載される、オオシマノミギセル(Clausilia buschii)を記載していました。しかし、この記載はまだ明確に「日本の陸貝」であることを示すものでは無いようでした。ただ、後年の日本ヨーロッパでの日本の貝類研究という意味では「萌芽期」だったと言えそうです。
黎明期(1847年)
しかし、1847年は、その日本の貝類学の芽が土から顔を出した「黎明期」でした。この年、ドイツの二大学者によって、日本の生物相を宣言するような学名が公表されたのです。
| 貝種(和名) | 記載時の学名 | 記載者 | 意味合い |
| ニッポンマイマイ | Helix japonica | ファイファー | 「日本」を冠した学術的宣言 |
| シイボルトコギセル | Phaedusa sieboldii | キュースター | シーボルトへの献名 |
シーボルト・コレクションが未分類で混乱していたことを推測すると、ファイファーがニッポンマイマイに「japonica(日本の)」という明確な学名を与えることができたのは驚嘆に値します。
これは、標本の形態から「この生物相は、日本の固有種である」と断定できるほどの詳細な分析を行った証拠であり、日本の生物相の存在を国際的に確固たるものにした「学術的夜明けの宣言」だったと言えるのでは無いでしょうか。また、キュースターのシーボルトへの献名も、そのコレクションの重要性を認識していたと思わせます。

ウスカワマイマイの学名に秘められた学者の使命
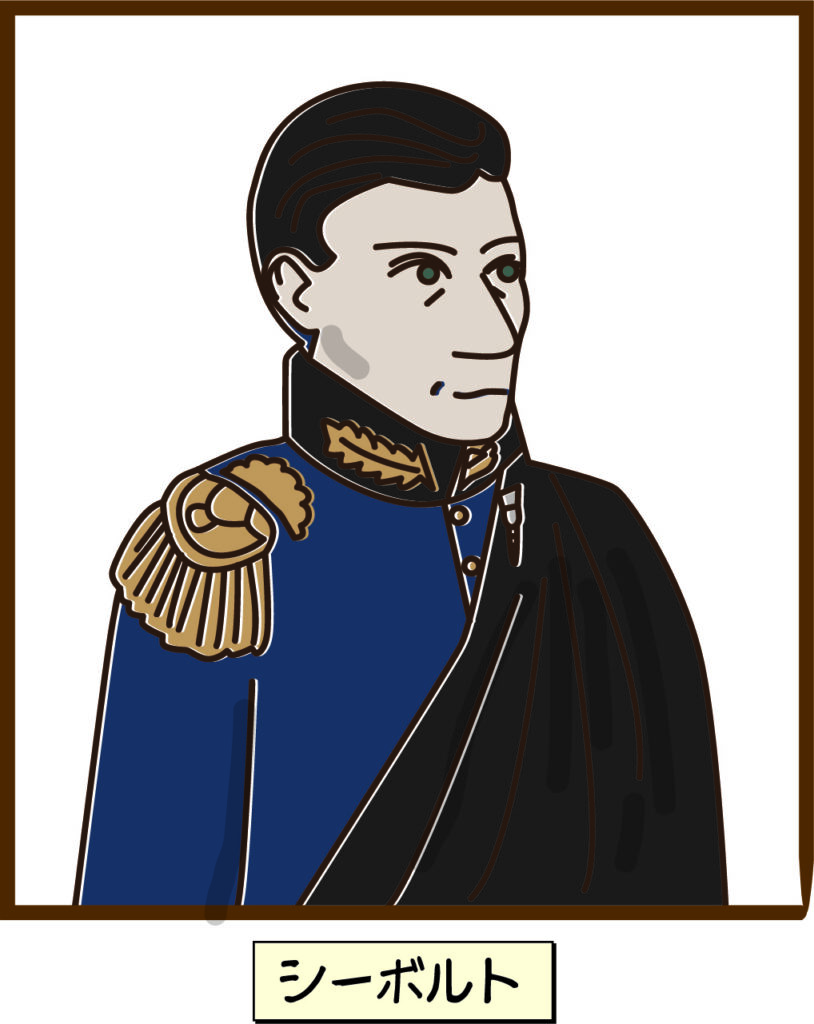
私が飼育しているウスカワマイマイの学名Acusta sieboldtiana (Pfeiffer, 1850)は、この黎明期の直後、1850年に記載されました。
ファイファーは、この種に改めてシーボルトへの献名「sieboldtiana」を与えています。これは単にシーボルトに畏敬の念を抱いたという感情的な側面だけでなく、分類学者としての強い使命感があったと推測できます。
それは、情報が錯綜し「モルッカ諸島」説さえあった標本に、シーボルトの名を刻むことで、その標本の出所(日本)と価値を学術的に公表し、コレクションの研究を推進するという、意図があったのではと私は推測しています。
この献名こそ、「日本の陸貝の多様性の価値を正しく認識しよう」という、19世紀の分類学者からの「学術的警鐘」だったのではないでしょうか。
生物学者の知のバトンリレー
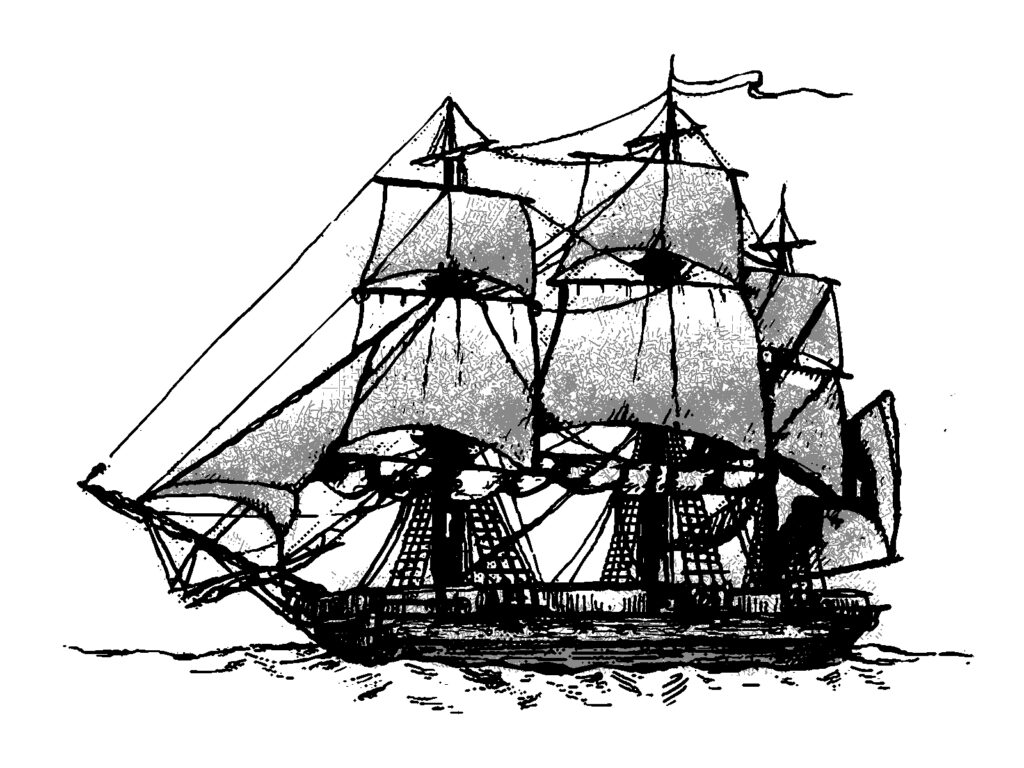
ファイファーやキュースターなどの初期の記載を整理し、日本の貝類分類学を体系化したのが、冒頭で引用したマルテンスです。彼は、1860年にプロイセン政府によるThetis号の極東海洋調査航海に参加し、その後15カ月間にわたる東南アジアの海域で日本の貝類を含む生物調査を自ら行い、日本の貝類相の全体像を確立しました。
シーボルトが開拓し、ファイファーとキュースターが学名として打ち立て、マルテンスが体系化する。この流れこそが、現代の日本の貝類分類学の揺るぎない基礎となって行ったのです。
来る2047年のカタツムリの研究は🤔
ウスカワマイマイの学名には、鎖国時代の日本とヨーロッパの学術界を結んだ、170年以上にわたる知の物語が凝縮されています。
そして、日本の分類学が国際的な学術舞台に上がった1847年から丁度100年後の1947年には、日本の貝類学を長らく牽引した偉大な学者、黒田徳米博士が京都帝国大学(現:京都大学)で博士号を取得されています。これは、日本の研究者が自国の生物相を自力で解明する時代へと突入した、記念すべき節目です。
Courtesy Malacological Society of Japan.
この100年周期の巡り合わせを考えると、さらに100年後の2047年には、AIやゲノム解析といった最新技術が、日本の陸貝の多様性を根本から覆すような、驚くべき新事実をもたらすかもしれませんね。
(なお、今回の参考については、インターネットのアーカイブなどを参考にしています。もし、記載に間違いや訂正事項がございましたら、ご指摘いただけますと幸いです。)
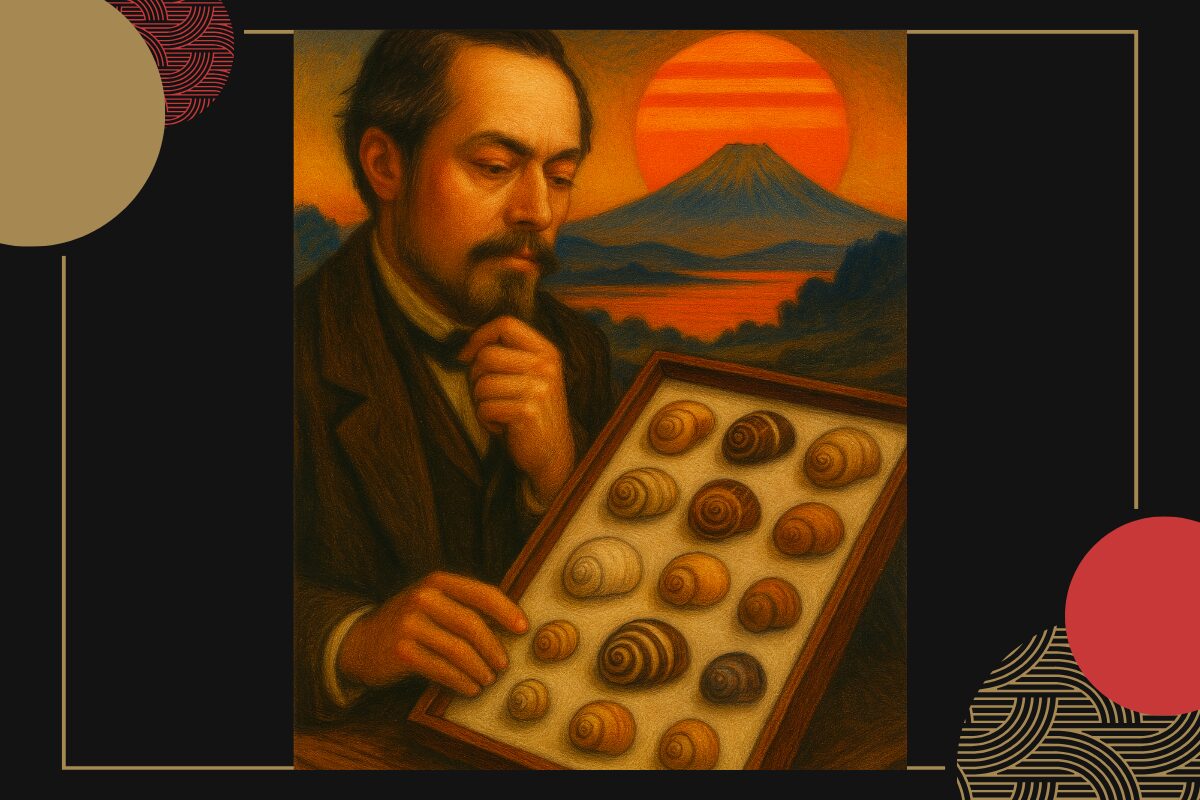


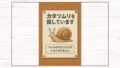
コメント