
「でんでんむしむし、カタツムリ〜♪」
子どもの頃に誰もが一度は口ずさんだことがある歌ですね。短い歌詞ですが、不思議と耳に残り、今でも梅雨の季節になると自然に思い出す方も多いのではないでしょうか。今回は、この「カタツムリの歌」にまつわる歴史や由来などを考察します。
「カタツムリの歌」の誕生

「カタツムリの歌」が初めて登場したのは、1911年(明治44年)に刊行された『尋常小学校唱歌(一)』。
作詞者は明確には分かっていませんが、「早春賦」を作詞した吉丸一昌(よしまる・かずまさ/1873〜1916)ではないかと考えられています。
その後、1932年(昭和7年)の『新訂尋常小学唱歌 第一学年用』にも収録され、全国の小学校で歌われるようになりました。
歌詞はとてもシンプルです。
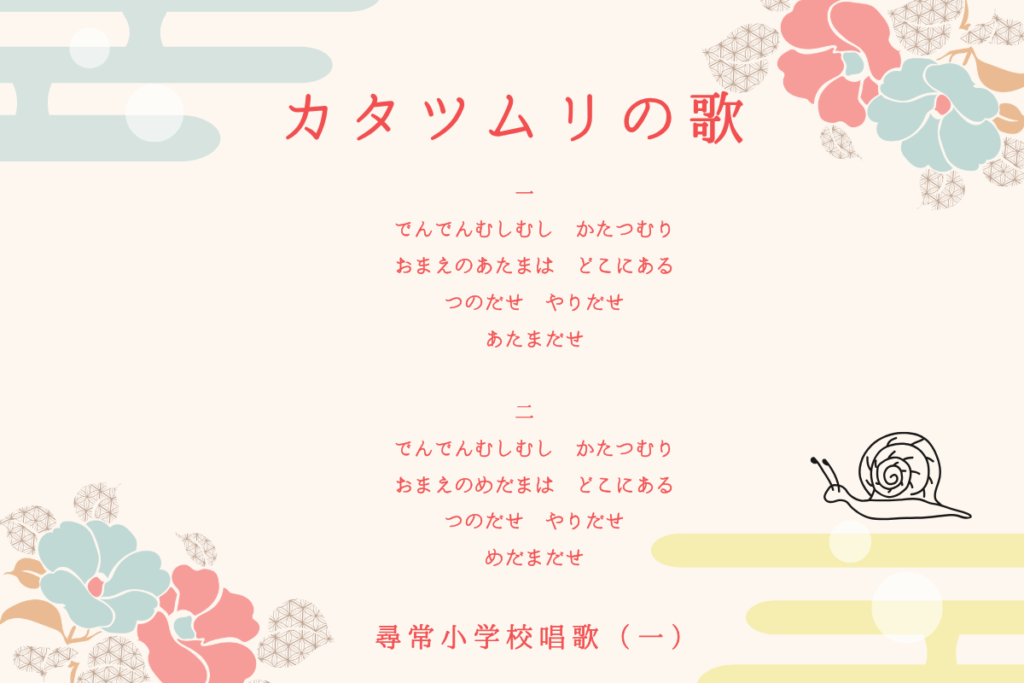
子どもたちが自然と一緒に遊ぶような感覚がそのまま歌になっていますね😃
大正時代と童謡運動
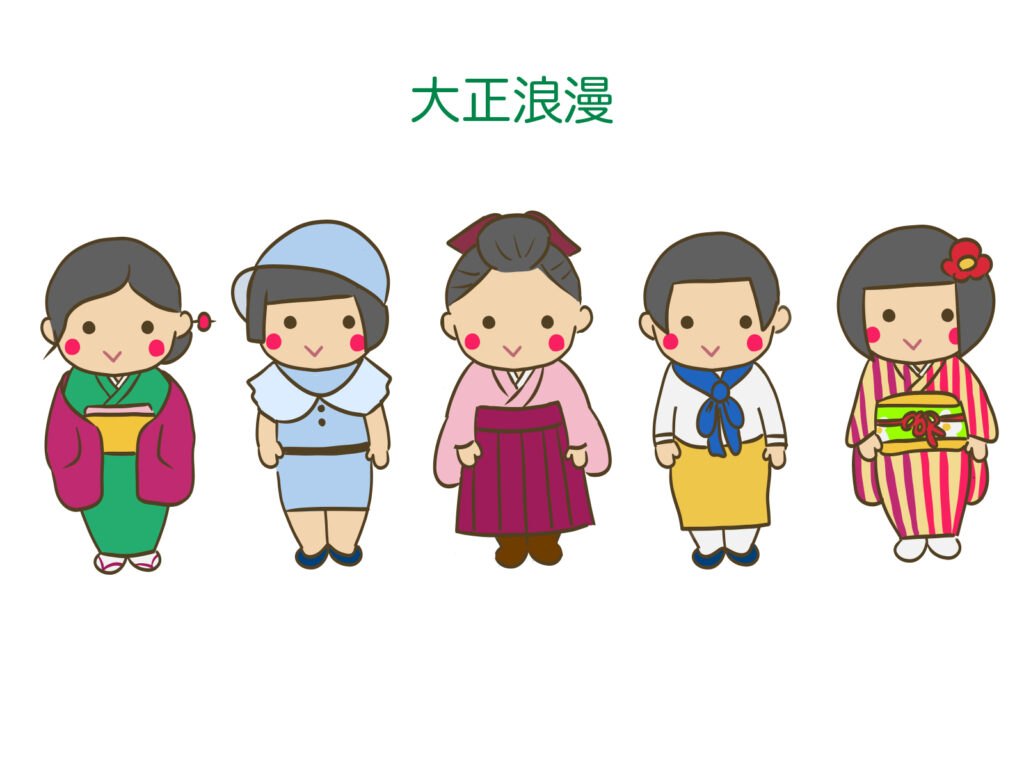
この歌が広まった背景には、大正時代の「童謡運動」があります。
1918年(大正7年)、児童文芸雑誌『赤い鳥』が創刊されました。代表者は鈴木三重吉。北原白秋、西条八十、野口雨情といった詩人たちが参加し、子どもにふさわしい文学や歌を生み出していきました。
この大正期の童謡運動は、大正デモクラシーの自由主義的な風潮の中で育まれました。難解な唱歌ではなく、子どもの感性や空想を大切にした歌を作ろうという動きだったのです。
「かなりや」(西条八十)
「十五夜お月さん」(野口雨情)
「赤い鳥小鳥」(北原白秋)
いずれも、今も歌い継がれる名曲たちです。
このような流れの中で「カタツムリの歌」も、子どもにとって親しみやすい自然の歌として定着していきました。
「ツノ出せ、ヤリ出せ」ってなに?

歌詞の中で印象的なのは「つのだせ、やりだせ」というフレーズ。実はこの部分には諸説あります。
- 触覚説:カタツムリの大きな触角(先に目がある)と小さな触角を指しているとするもの。
- 恋矢(ラブダート)説:カタツムリが交尾の際に使う「恋の矢(レンシ)」を指すとするもの。
専門家の中には恋矢説を紹介する方もいますが、実際に恋矢を観察できるのは飼育者でもごく稀なことです。一般的には、触覚を指すと考える方が自然でしょう。
とはいえ、「どちらが正解」というよりも、地域の言い伝えや昔の子どもたちの感覚によって解釈はさまざまに広がっていたのかもしれません。歌詞の背後にある多様な想像力を感じると、童謡の奥深さに気づかされますね。
「カタツムリの歌」は、子どもが自然と対話する歌

「カタツムリの歌」は、子どもが自然と対話する歌です。
小さな生きものに声をかけることで、命へのまなざしや親しみが育まれていきます。
カタツムリは雨や梅雨のイメージと結びつき、日本の季節感を象徴する生き物でもあります。
梅雨時に口ずさむこの歌は、日本の風土や文化と深くつながっているのです。
しかし一方で、現代の子どもたちが実際にカタツムリを見つけたり触れたりする機会は減ってきています。歌だけが残って、生き物の実体験が伴わないことは少し寂しいことでもあります。
自然の中でカタツムリを見かけたら、ぜひお子さんやご家族と一緒に口ずさんでみてください。そして実際に庭先や公園で、ゆっくり歩くカタツムリを探してみましょう。
歌と自然が結びついた時、童謡が本当に生き生きと息づくのではないでしょうか😊



コメント