
私は、先日の夜、カタツムリのお世話が終わった後、以前から興味を持っていたカタツムリの食性を観察するために、一晩、折り紙を与えてみました。今回は、その「折り紙を食べるカタツムリ」について考察しました🤔
ある晩のカタツムリへのお試しご飯

以前から、「カタツムリは折り紙を食べる」ということは知っていました。しかし、もしかしたら、カタツムリに害があるのでは🤔と思い、折り紙を与えることはしていませんでした。
しかし、先日の夜に、あるホームページで「折り紙の塗料には、カタツムリの好きな炭酸カルシウムが含まれている」という内容の記事をたまたま読んだのです。
そのため、折り紙を一晩だけ上げてみました😊

一晩たって、翌朝、見ると、折り紙がボロボロになる程でした😅
かなり、折り紙が気に入った様子でした😋
折り紙を食べた理由──セルロースと炭酸カルシウム
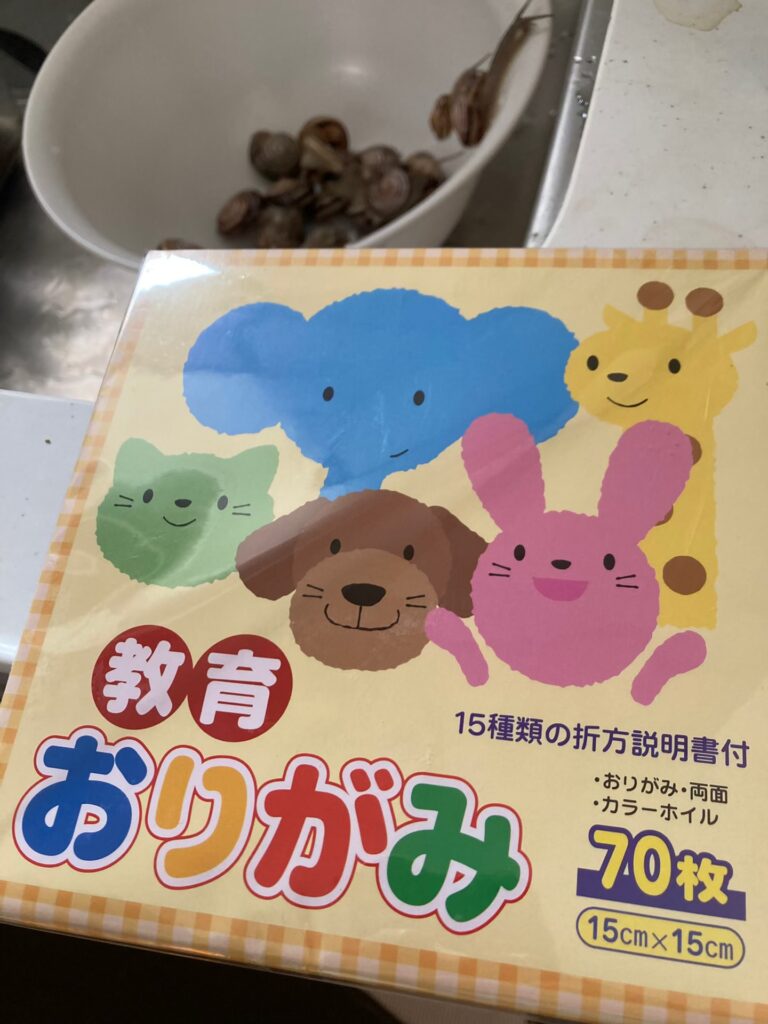
いろいろ、調べてみると、折り紙や色紙には、カタツムリにとって魅力的な2つの成分が含まれている事が分かりました。
- セルロース:植物の繊維。紙の原料。
- 炭酸カルシウム(CaCO₃):色紙の白色度を上げるための塗料や添加剤。カタツムリの殻の原料でもある。
炭酸カルシウムは、殻の修復や成長に欠かせないミネラルです。
野外では石灰岩やブロック屏をかじるカタツムリの姿が知られています。

一方で、セルロースは植物の細胞壁の主成分であり、カタツムリが分解・吸収できる数少ない動物の一種でもあります。
カタツムリにはセルラーゼ(セルロース分解酵素)が体内に存在し、落ち葉や木の皮、紙類を栄養源にすることができるのです。

ふと思い付いた、私の仮説💡
今回の観察から、私はある仮説を考察しました。
なお、あくまでも空想の域を超えない内容ですが、こんな可能性があったら凄い事だなと思うのです🤔

カタツムリは、セルロースからキチン質を合成している可能性があるのではないか?
私のひらめきの空想😶🌫️
カタツムリの歯舌(しぜつ、ラディラ)と呼ばれる器官は、非常に精密な「キチン質」の歯が何万本も並んだ構造で、常に新しく作られ、摩耗と再生を繰り返しています。
また、カタツムリの表面にはキチン質で構成された殻皮(かくひ)と呼ばれる薄膜があり、石灰質でできた殻の表面を覆っています。
ちなみに、殻皮はカタツムリに限らず貝類のほとんどの種類に存在し、石灰質の殻本体を保護する役割があります。

人間もセルロースを分解できるのか🤔
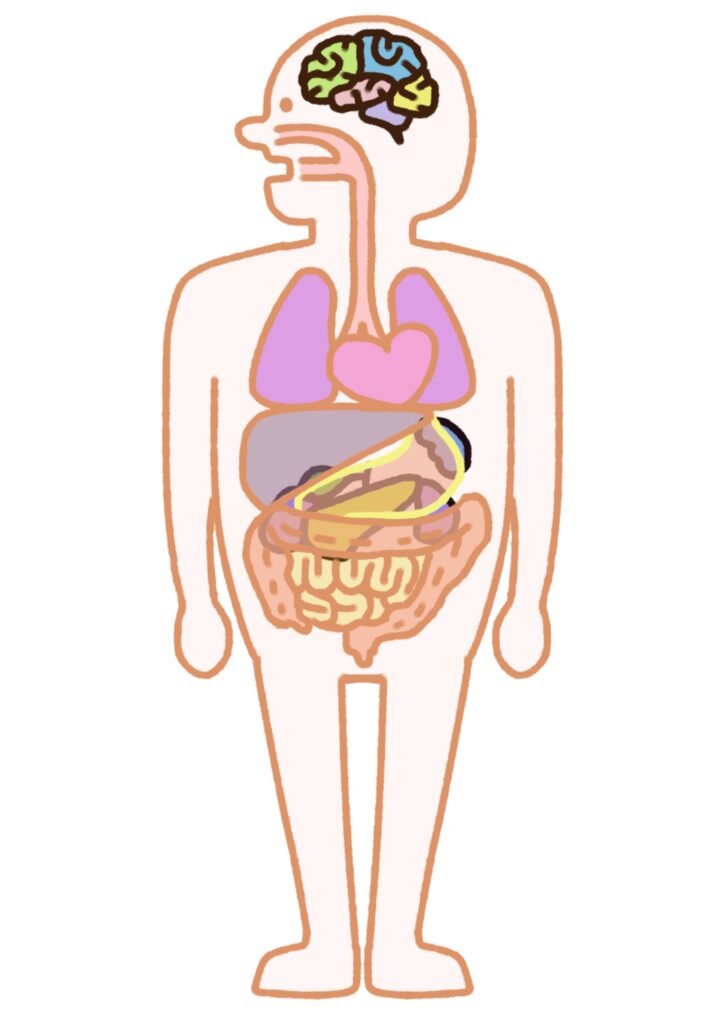
しかし、私たち人間には、セルロースを分解する能力も、そこからキチンを生成する酵素系もありません。
もし本当にカタツムリが、「セルロース → グルコース → グルコサミン → キチン」という生化学的な変換プロセスを持っていたとしたら?
それは、人間の科学技術では未だ不可能な「物質変換=錬金術」を、彼らが日常的に行っているということになるのです。
こんな仮説が成り立つなら、それはもしかしたら、驚きの発見につながるかもしれません😌
カタツムリは想像力を掻き立ててくれる生き物
カタツムリというのは、いつも私の想像力を掻き立ててくれる存在です😊
もし、皆さんのご自宅のカタツムリに折り紙を試してみてください。カタツムリは、折り紙と同じ色のう⚪︎ち💩をしますよ😄




コメント